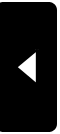2013年05月23日
八重の桜の山本覚馬

信念の人 山本覚馬
点字毎日「伝説の隣人たち」 96号より
NHK大河ドラマ「八重の桜」。
「ならぬことはならぬ」の言葉にはまっています。
八重の兄の山本覚馬。西嶋秀俊さん、素敵です。
山本覚馬は、視力を失い脊髄の損傷のため、一人では歩くことも困難な体で、京都の文明開化の先頭に立ち、近代京都の基礎を作った人です。
テレビでも放映されているように、会津藩砲術指南役の長男として生まれ、江戸で砲術を学びながら、欧米の軍事技術や文化を学びます。
国に帰った覚馬は、藩主・松平容保とともに京都へ移り、幕末の動乱の中に身を投じます。
鳥羽・伏見で新政府と戦ったときに捕えられ、幽閉されたときに眼病が悪化して失明。
脊髄を悪くして足が不自由になっても、口述筆記で、新しい国の体制を論じた「管見(かんけん)」は西郷隆盛らをも驚かせ、釈放されると、岩倉具視のすすめで、京都府の顧問に就任します。
敵であった会津藩士としては、異例の転身だったようです。
覚馬は次々と改革を実施し、日本初の小学校を設立。
西陣織などの伝統産業を助成、輸出の促進をし、殖産興業の礎を作っています。
また、八重の夫になる新島襄と知り合い、キリスト教と近代科学を教える学校を作りたいという新島に、自分の土地を提供します。
そこに建てられたのが、現在の同志社大学です。
明治12年には、京都府議会選挙で当選し、初代議長になります。
覚馬は、64歳まで生き、第二の故郷、京都でその生涯を終えます。
八重の生涯とともに、覚馬の生涯もこれから楽しんでみたいです。(ののちゃん)
Posted by ののちゃん at 08:00
│情報